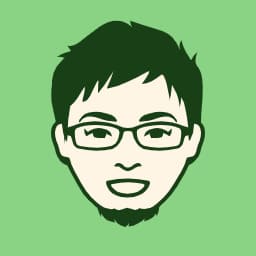
ども。
ウバかず(@UberSaitama)です!
埼玉西部のド僻地でウーバーイーツの配達をしています。
基本、超まったりな配達パートナーです。
都労委、ユニオンに団体交渉権利、認める
「Uber Eats」の配達パートナーが労働組合を作って、団体交渉を求める権利があるかどうかについて、「東京都労働委員会」(以下、都労委)が2022年11月25日、“権利がある”とする命令書を交付しました。
世界的に見ても、配達パートナーなどネット・アプリなどを介して単発の仕事を請け負う“ギグワーカー”の法的な立場は判断が分かれている部分ですが、日本においては労働者としての権利を認めた初めてのケースと言えそうで、多少なりとも影響が出てもおかしくはなさそうです。

今回のケースでは、労働組合である「ウーバーイーツユニオン」が、運営側に対して、配達中の事故に遭った場合の補償であったり、報酬額の決定に対して透明性を求めて団体交渉を要求していました。
ただ運営側はこれを拒否。
配達パートナーはあくまでも“個人事業主”であるコトから、労働組合法で保護の対象としている「労働者」には当たらないと言うのが、運営側の主張だったのですが、今回の命令書は、こうした運営側の主張に対して、労働組合側が都労委に救済を申し立てていた結果です。

ひとまず結論をまとめてみます。
- 配達パートナーが労働組合法上の労働者に当たるかどうか
- 労働環境が変わるかどうか
結局のところ、この2点だと思うのですが、まずは労働組合法上の労働者に当たるかどうか。
これに該当しないと、団結権・団交権・団体行動権が得られないと言うコトになります。
専門家ではないので、詳細は省きますが、具体的にこの3つの権利は、こんな内容。
・団結権…労組を組織する、参加する権利
・団交権…労働条件などを労使で交渉できる権利
・団体行動権…要するにストライキ
今回の都労委による命令書は、これらの労働組合法上の権利を認めると言う内容のモノ。
つまりは団体交渉を労働組合側が求めれば、拒否すると不当労働行為が発生すると言うコトで、「団交権」は憲法上で認められている権利なので、会社側はこれに対して、誠実な対応を行う必要性が出てきます。
つまり、会社側の主張に対し、その根拠を資料などで提示した上で交渉に当たる必要が出てきます(これも行わなければ不当労働行為が成立する可能性がある)。
もちろん、団体交渉は、あくまでも交渉に過ぎず、そこで譲歩しなければならないと言う訳でもない。
ただ明らかにかなり前進した内容になったと言うのは、間違いがなさそう。
あくまでも団体交渉権を認めただけだが…
ただ間違ってはいけないのは、あくまでも今回の内容は、“団体交渉をする権利がある”と言うコトを認めただけ。
ギグワーカーの権利を認めた訳でもなければ、法的な立場を明確にした訳でもない。
都労委自体は、「Uber Eats」の配達パートナーについて、労働基準法上の雇用に当たるかどうか。
それを判断した訳でもない。
ここは間違ってはいけない部分。
労働基準法上の雇用に当たるとすれば、働く上で、賃金・時間・休暇などがしっかりと定められている訳ですが、現状、「Uber Eats」の配達パートナーは適用されない状態。
だからこそ多種多様な働き方ができている訳だけれども、世界的に見ると、「Uber Eats」のhファイ立つパートナーなどのギグワーカーが、雇用に当たるかどうかは判断が分かれているところ。
ただ世界を見渡してみると、何かしらの判断が出ていると言うのも事実であり、今回の都労委の結果が日本におけるギグワーカーの労働体系に1つのメスを入れたとも言えそう。

またそもそも「Uber Eats」の配達パートナーは、全国で13万人程度いると言われている(会社側の発表だが、実際に1ヶ月の内で常時稼働がある配達パートナーは、もっと少ない)。
「ウーバーイーツユニオン」を構成するのは、約30人。
団体交渉をユニオン側が望めば、応じる必要が出たと言うのは、画期的な話ではあるけれど、やはり配達パートナーの数に対して、ユニオンの加入率は著しく低く、配達パートナーを代表している状態とは言えないのも実情。
この辺りが、今後、どう影響して行くのかな…と言う感じには思えますが、ユニオン側から見れば、まず第1歩と言う感じなのは、間違いなさそうですね。

Win-Winな関係になれるのか
個人的な賛否は、現状ではまだ考えにくい部分がある。
そもそもユニオンが何を求め、どこまでを求めているのかも不明だし。
ただ声を上げると言うのは、間違っていないとも思う。
ただその結果、「Uber Eats」が持つメリットを失わせなければ良いな…とも。
働きたい時に、働きたい場所で、働きたい時間、働く。
それが何よりものメリット。
専業であろうが、副業であろうが、そう言う部分では働きやすいのが「Uber Eats」ではあるけれども、やはり現状、グレーな部分もあるようには思う。
ただそこが法的な部分でがんじがらめになると、人材を確保せずに進めてきたビジネスが破綻しかねないようにも思う。
果たしてそれが、Win-Winの関係になるのだろうか。
配達パートナーの人数が多いだけに、それぞれの働き方がある。
専業の人と、副業・兼業の人では求めるモノも少しは異なるでしょうしね。
その辺り、ユニオンがバランス感覚を持って運営しているのであれば、今後に期待したいなぁ…とは思うけれど、実態はどうなんでしょうね。
ただギグワーカーであるコトを踏まえて、自由を謳歌している訳で、その分、失っている権利があるのは仕方がない話だとも思うんですけれどもね、個人的には。
なので欲を言えば、もうちょっと報酬額決定に際しての透明性が高まれば…ぐらいで。
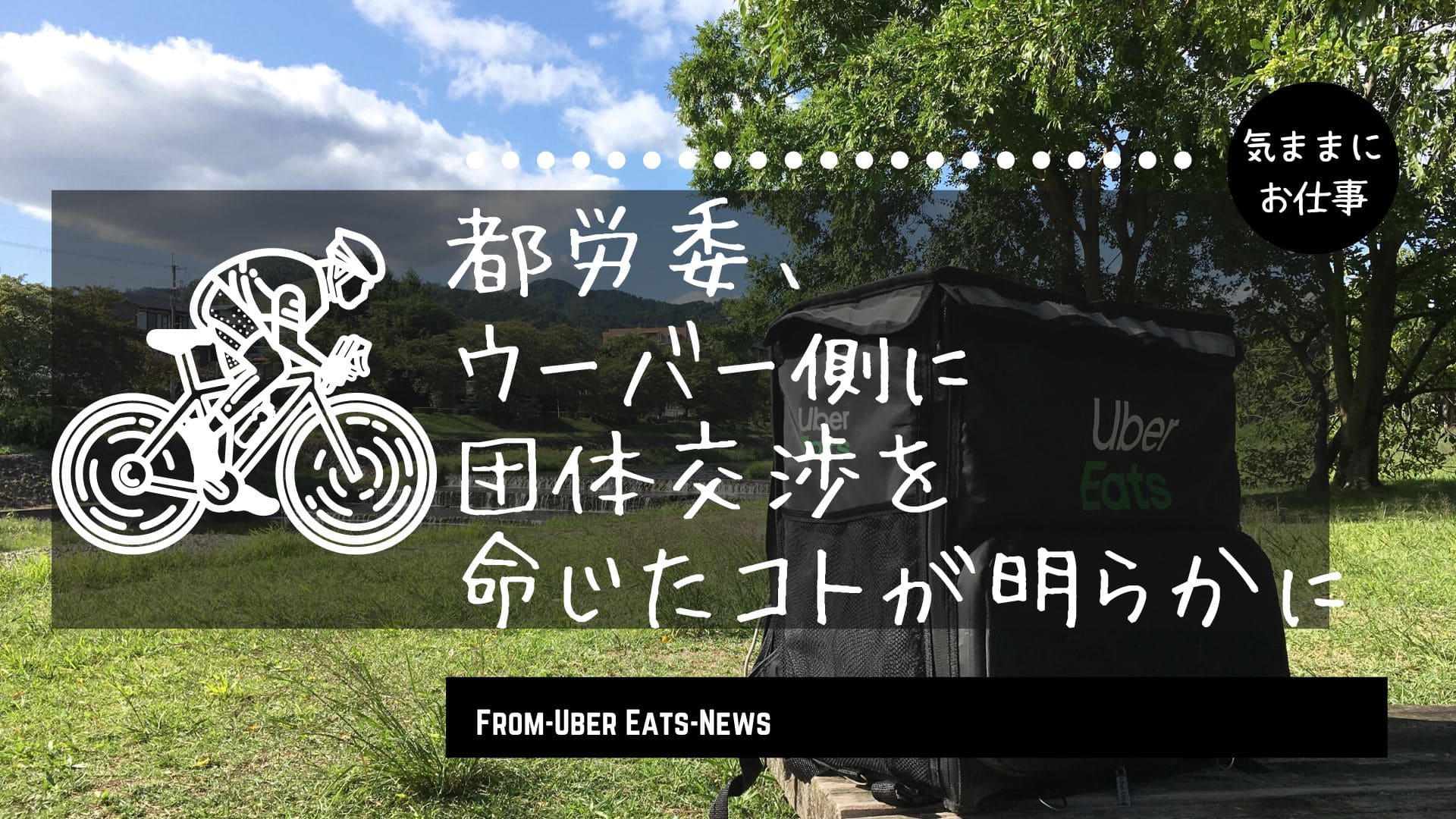
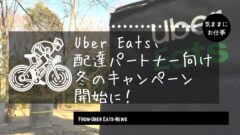

コメント